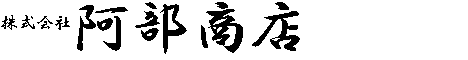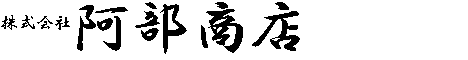|
|
 |
| 一般的な本格焼酎 |
 本格焼酎と言って思いつくものはどんなものがありますでしょうか。現在生産されている本格焼酎は主要なものとして以下のものがあげられます。 本格焼酎と言って思いつくものはどんなものがありますでしょうか。現在生産されている本格焼酎は主要なものとして以下のものがあげられます。
●米焼酎
●麦焼酎
●いも焼酎
●黒糖焼酎
●そば焼酎
●泡盛
●粕取り焼酎
この項ではこれらの焼酎の特徴とそれ以外の本格焼酎を紹介します。
|
| |
| 米焼酎 |
 米と米麹から作られる焼酎です。後述する粕取り焼酎は清酒を醸造した酒粕から蒸留されますが、米焼酎は米を精米し、米麹と掛け合わせることで生産されます。主な生産地は熊本県人吉市を中心とする球磨盆地です。また、最近では清酒蔵が清酒製造の閑散期に米焼酎の蒸留をすることが増えており、全国各地で米焼酎が生産されるようになっています。 米と米麹から作られる焼酎です。後述する粕取り焼酎は清酒を醸造した酒粕から蒸留されますが、米焼酎は米を精米し、米麹と掛け合わせることで生産されます。主な生産地は熊本県人吉市を中心とする球磨盆地です。また、最近では清酒蔵が清酒製造の閑散期に米焼酎の蒸留をすることが増えており、全国各地で米焼酎が生産されるようになっています。
香りや味わいは吟醸酒に近く、比較的焼酎初心者でも取っつきやすい本格焼酎といえます。従来、減圧蒸留(用語集参照)で作られる銘柄が主流でした。しかし、このところの本格焼酎ブームで米焼酎が本来持っている香りや味わいを見直す動きが大きくなり、それにともなって従来の製法で作られた米焼酎が徐々に増えてきています。
|
| |
| 麦焼酎 |
 大麦と大麦麹、あるいは米麹から作られるのが一般的です。従来大都市圏では本格焼酎といえば麦焼酎というイメージがありました。これは三和酒類の「いいちこ」や二階堂酒造の「二階堂」の知名度によるところが大きく、昭和50〜60年代の第一次本格焼酎ブームの際には二階堂のとっくりやいいちこのボトルをキープしておくのが流行りました。今回の本格焼酎ブームの素地を作ったのは「いいちこ」や「二階堂」と言っても良いと思われます。 大麦と大麦麹、あるいは米麹から作られるのが一般的です。従来大都市圏では本格焼酎といえば麦焼酎というイメージがありました。これは三和酒類の「いいちこ」や二階堂酒造の「二階堂」の知名度によるところが大きく、昭和50〜60年代の第一次本格焼酎ブームの際には二階堂のとっくりやいいちこのボトルをキープしておくのが流行りました。今回の本格焼酎ブームの素地を作ったのは「いいちこ」や「二階堂」と言っても良いと思われます。
さて、このように大分の名産品という印象の強い麦焼酎ですが、元々は長崎県壱岐地方で長らく生産されてきたものであり、数百年の歴史を持ちます。麦焼酎といえば大分というイメージが強くありますが、これはここ30年くらいのイメージであり、歴史的には壱岐焼酎が麦焼酎の元祖となります。
味わいや香りは同じ麦から作られるウイスキーに近く、洋酒がお好きな方が本格焼酎になじむにはもっとも適切といえるでしょう。
前述しましたとおり、大分県と長崎県壱岐島が生産拠点です。
大分では、減圧蒸留(用語集参照)・イオン交換樹脂(用語集参照)という手法で作られることが多く、すっきりとした飲み口の麦焼酎が主流です。
また、最近では常圧蒸留(用語集参照)を使用して、個性ある製品を出している蔵も登場しています。
一方、壱岐では伝統的な製法(主原料は麦、麹は米麹、常圧蒸留、米麹と麦の配合比率は約1:約2)を守る7軒の蔵が残り、個性を競っています。
|
| |
| いも焼酎 |
 さつまいもと米麹、あるいはさつまいも麹から作られます。さつまいもはでんぷん質が少なく、麹にしてもアルコールが出来にくいため、一般的に米麹で仕込みます。鹿児島県が一大生産拠点であり、鹿児島で酒と言えばいも焼酎のことを示します。第一次焼酎ブームの際には「すっきり」「さっぱり」という流れだったため、香りが濃厚で味わい深いいも焼酎は「臭い」「くどい」と見られてしまい、注目されませんでした。 さつまいもと米麹、あるいはさつまいも麹から作られます。さつまいもはでんぷん質が少なく、麹にしてもアルコールが出来にくいため、一般的に米麹で仕込みます。鹿児島県が一大生産拠点であり、鹿児島で酒と言えばいも焼酎のことを示します。第一次焼酎ブームの際には「すっきり」「さっぱり」という流れだったため、香りが濃厚で味わい深いいも焼酎は「臭い」「くどい」と見られてしまい、注目されませんでした。
味わいは甘い舌触りが特徴で、香りは米や麦に比べて際だちます。これは麦や米と異なり、常圧蒸留(用語集参照)で蒸留されることが多いこととさつまいも自体の香りや甘みが米や麦と違って強いことが理由と考えられています。
|
| |
| 黒糖焼酎 |
 黒糖を使用した酒類は通常リキュール類などに該当し、税率が焼酎とは異なる高税率となります。しかし、日本復帰前から奄美諸島で生産され、名物となっていた黒糖焼酎を何とか生かすために 黒糖を使用した酒類は通常リキュール類などに該当し、税率が焼酎とは異なる高税率となります。しかし、日本復帰前から奄美諸島で生産され、名物となっていた黒糖焼酎を何とか生かすために
必ず麹を使用して仕込むこと
大島税務所管内のみの特例とする
という2点の条件で特別に認可されました。そのため、他の焼酎が法律的には日本全国で生産できるのに対して、黒糖焼酎は奄美諸島でしか生産できない特別な名産品となっています。
砂糖に由来している黒糖焼酎は黒糖独特の香りと甘い味わいが特徴です。焼酎ですから当然糖分は一切含まれていません。そのため、女性に人気が高く、注目されています。
|
| |
| そば焼酎 |
 そば焼酎は今までに紹介した焼酎に比べて歴史の浅い焼酎です。1973年に雲海酒造によって初めて開発されたそば焼酎は、麦焼酎とともに第一次焼酎ブームの牽引役となりました。現在では長野や北海道といったそばどころを中心に全国で作られています。 そば焼酎は今までに紹介した焼酎に比べて歴史の浅い焼酎です。1973年に雲海酒造によって初めて開発されたそば焼酎は、麦焼酎とともに第一次焼酎ブームの牽引役となりました。現在では長野や北海道といったそばどころを中心に全国で作られています。
そば焼酎は、ほのかにそばの香りが漂い、舌の上にそば独特の甘さが残る焼酎です。そのため、ロックが大変に美味しく「そば焼酎といえばロック」という人も多くいます。ロックだけでなく、おそばを茹でた茹で汁であるそば湯で割ると上質のそばを食べているような心地がします。
蒸留をしているとはいっても、そば焼酎はそば由来の焼酎ですので、そばアレルギーをお持ちの方は飲み方や体調に十分ご注意ください。
|
| |
| 泡盛 |
 沖縄で作られる伝統の蒸留酒が泡盛です。泡盛は黒麹菌という麹菌を米に付けて作られることが条件となっており、主にタイ米で醸し出されています。また、他の焼酎がまず麹を発酵させ、そこへ原材料を投入して二次発酵を行うのに対して、泡盛は黒麹菌をタイ米に付け、発酵させ、それをそのまま蒸留する一次仕込み・全麹という手法が用いられます。 沖縄で作られる伝統の蒸留酒が泡盛です。泡盛は黒麹菌という麹菌を米に付けて作られることが条件となっており、主にタイ米で醸し出されています。また、他の焼酎がまず麹を発酵させ、そこへ原材料を投入して二次発酵を行うのに対して、泡盛は黒麹菌をタイ米に付け、発酵させ、それをそのまま蒸留する一次仕込み・全麹という手法が用いられます。
泡盛の特徴は「古酒」(クースー)にあるといっても良いと思います。最近でこそ、他の焼酎でも長期熟成させた「古酒」(こしゅ)が出回るようになりましたが、もともと長期熟成させるという考え方は泡盛が一番根強くあります。これは何かお祝い事があったり、節目となる出来事があった際に泡盛を甕に入れ、保存しておくという琉球地方の習慣があったためです。第二次世界大戦で沖縄は焦土と化し、琉球王朝時代から延々と受け継がれてきた伝統の古酒もほとんど破壊されてしまいましたが、現在でもこうした習慣は残っており、100年後の子孫にこの伝統と平和を伝えるべく「百年古酒」という運動も行われています。
|
| |
| 粕取り焼酎 |
 今までの分類はすべてもろみを作り、そこからアルコール分を蒸留する「もろみ取り焼酎」です。実は焼酎にはもう一つ清酒などの搾り粕を使用して作る「粕取り焼酎」と呼ばれる焼酎があります。一時期だいぶ少なくなっていましたが、最近の本格焼酎ブームで徐々に復権しつつある種類の焼酎です。清酒を作ると搾り粕が残ります。この搾り粕に籾殻を混ぜて、下から他の焼酎と同様に熱風を送り込みます。そうするとアルコール分が抽出されます。このとき、籾殻の焦げたにおいがアルコール分とともに抽出されるため、大変にあくの強い、個性的な癖のある焼酎となります。 今までの分類はすべてもろみを作り、そこからアルコール分を蒸留する「もろみ取り焼酎」です。実は焼酎にはもう一つ清酒などの搾り粕を使用して作る「粕取り焼酎」と呼ばれる焼酎があります。一時期だいぶ少なくなっていましたが、最近の本格焼酎ブームで徐々に復権しつつある種類の焼酎です。清酒を作ると搾り粕が残ります。この搾り粕に籾殻を混ぜて、下から他の焼酎と同様に熱風を送り込みます。そうするとアルコール分が抽出されます。このとき、籾殻の焦げたにおいがアルコール分とともに抽出されるため、大変にあくの強い、個性的な癖のある焼酎となります。
本来、粕取りとはこのような手法で作られます。しかし、現在では吟醸酒を造る清酒蔵が増加し、それとともに清酒粕をもとにもろみを作り、これを蒸留する場合が増加しています。こうした籾殻を使用せずに清酒粕でもろみを作り蒸留することで日本酒と間違えるような香りの高い粕取り焼酎が増加しています。
もともと粕取り焼酎は早苗饗(さなぶり)という田植え後のお祭りで愛飲されていた庶民のお酒でした。ここから粕取り焼酎に「早苗響焼酎」という別名がついたのです。特に九州北部では早苗饗においては粕取り焼酎が飲まれており、かつては粕取り焼酎の専業蔵も存在していたほどでした。こうした伝統を復活させようという動きもあり、「九州焼酎探検隊」というホームページで籾殻を使用した粕取り焼酎に関する調査や研究が行われています。
また、実際に籾殻を使用した粕取り焼酎の醸造再開に向けた実験も行われているようです。ただ、焼酎ブームの陰で清酒の生産量が低下し、清酒粕も少なくなってしまっています。
この少ない清酒粕を粕漬けなどの分野がねらうため、ますます粕取り焼酎は製造の危機に瀕しています。
|
| |
| そのほかの焼酎 |
 これらの焼酎のほか、清酒をそのまま蒸留した清酒取り焼酎、栗を使用した栗焼酎、しそを使用したしそ焼酎、牛乳を使用した牛乳焼酎などが製品化されており、実際に店頭に並んでいます。 これらの焼酎のほか、清酒をそのまま蒸留した清酒取り焼酎、栗を使用した栗焼酎、しそを使用したしそ焼酎、牛乳を使用した牛乳焼酎などが製品化されており、実際に店頭に並んでいます。 |
| |
|